
歴史は鏡である
 「歴史は鏡である」とよく言われますが、過去の政治や社会経済・文化を調べ、そこから読み取れる特徴や問題点を考え、良い点を現在や未来に活かすことを目指す学問です。皆さんも、身近な地域の歴史や、関心のある歴史上の人物・出来事などを調べ、その意義や役割を考えてみてください。きっと、いろいろな発見があり、歴史を学ぶことの面白さを実感することでしょう。
「歴史は鏡である」とよく言われますが、過去の政治や社会経済・文化を調べ、そこから読み取れる特徴や問題点を考え、良い点を現在や未来に活かすことを目指す学問です。皆さんも、身近な地域の歴史や、関心のある歴史上の人物・出来事などを調べ、その意義や役割を考えてみてください。きっと、いろいろな発見があり、歴史を学ぶことの面白さを実感することでしょう。
担当授業
- 基本科目
-
- 歴史学の基礎
- 実践科目
-
- ゼミナール
- 卒業研究
- 教職科目
-
- 日本史概論
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 日本中世史
- 研究テーマ
-
- 戦国期の権力と社会
- 中世都市と流通・交通
- 中世職人論、石造物と石材流通
- 歴史地震と前近代社会
連絡先
- 研究室
- 14503
- ichimura@dce.osaka-sandai.ac.jp
学生時代は学生の特権を利用しよう
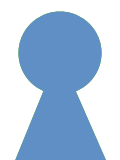 近頃、授業よりもアルバイトを重視している人が増えています。
もちろんアルバイトから学ぶことも多いでしょうが、卒業したら嫌というほど働かなければなりません。
大学時代は、学生の特権を利用して、今だからこそ十分できること、つまり学問、読書、クラブ活動などに時間を費やしてもらいたいと思います。
近頃、授業よりもアルバイトを重視している人が増えています。
もちろんアルバイトから学ぶことも多いでしょうが、卒業したら嫌というほど働かなければなりません。
大学時代は、学生の特権を利用して、今だからこそ十分できること、つまり学問、読書、クラブ活動などに時間を費やしてもらいたいと思います。
担当授業
- 基本科目
-
- コミュニケーション英語
- 展開科目
-
- 英米文化論
- 実践科目
-
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 英米文学
- 研究テーマ
-
- 18世紀イギリスのゴシック小説、アメリカのゴシック小説
-
18世紀にイギリスで流行った古典ゴシック小説と、その影響を受けて生まれたアメリカのゴシック小説の研究。
- アンブロース・ビアスの短編小説
-
19世紀アメリカの短編小説作家ビアスは、「意外な結末」で終わる作品を多く書いている。 結末で驚かされることで、読者は何を学ぶのか、また作者の意図は何かについて研究。
連絡先
- 研究室
- 14207
- kanzaki@dce.osaka-sandai.ac.jp
内なる文化を探究しよう
 私たちは、成長する過程で、無意識のうちに、地域の言葉、食物、風習、さらに東西の宗教、芸術、芸能、思想など様々な文化を吸収し、内なる文化を形成します。
そのような内なる文化に気づき探究していくと、自らも大きな歴史の流れの中に位置していることが分かってきます。
どうかこの学科で内なる文化と対話する醍醐味を味わってください。
私たちは、成長する過程で、無意識のうちに、地域の言葉、食物、風習、さらに東西の宗教、芸術、芸能、思想など様々な文化を吸収し、内なる文化を形成します。
そのような内なる文化に気づき探究していくと、自らも大きな歴史の流れの中に位置していることが分かってきます。
どうかこの学科で内なる文化と対話する醍醐味を味わってください。
担当授業
- 基本科目
-
- 社会学の基礎
- 展開科目
-
- 文化社会学
- 社会変動論
- 実践科目
-
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 社会学
- 研究テーマ
-
- 近世思想と日本の近代化
-
江戸社会は、近代日本に連続する合理的思想と非合理的思想を生成した。 前者では横井小楠や福沢諭吉の思想が、後者では水戸学や国学の国体論が重要である。 これらの思想と日本の近代化の関係を解明したい。
連絡先
- 研究室
- 14405
- kitano@dce.osaka-sandai.ac.jp
かけがえのない存在――自分を愛そう
- 好きなことをとことんやってほしい。それを貫くためには嫌いなこともやらないといけなくなる。
- いろんなことに好奇心を持ってほしい。それが探究心につながる。
- インターネットだけでなく、伝統的なメディアである書物に親しんでほしい。学生時代に読んだ本は一生の宝物になる。
- 日本語のコミュニケーション能力を育成したい。
- 自分を大事にしてほしい。他の誰とも違うかけがえのない存在である自分を愛してほしい。それは同じようにかけがえのない存在である他人を愛することにもつながる。

卒論のテーマは文学、演劇、映画、コミックやアニメなど表現文化作品の解釈。 もちろん、ヨーロッパの衣食住や環境問題、メディア事情などもOK。 やりたいことを見つけようとしている学生をサポートしたい。
担当授業
- 基本科目
-
- ドイツ語
- ドイツ語海外研修
- 展開科目
-
- コミュニケーション論
- 実践科目
-
- コミュニケーション演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- ドイツ文学
- 演劇
- 研究テーマ
-
- ブレヒトの演劇と演劇論
-
20世紀の劇作家ブレヒトは今や「ゲーテ以後最大の作家」「シェイクスピアとならぶ劇作家」と祀り上げられている観もあるが、 テキストを文化環境との関連で丁寧に解釈するというのが、私のスタンスである。
- 演劇におけるロールプレイ
-
演劇におけるロールプレイを、ドイツ演劇などの外国演劇や現代日本演劇をテキストに分析する。 それは、「世界は舞台」というトポスやメタシアター、演劇的なものの本質に迫るテーマであると思う。
- 19世紀後半から20世紀初頭における「文化」の意味作用
-
現代文化の源とも言える19世紀後半から20世紀初頭の時代。「服装」、「消費」、「都市」、「庭園」 …など様々なものが、文学的・非文学的テクストの中で、どのような意味作用を行っているかを分析する。
連絡先
- 研究室
- 14411
- ホームページ
- http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~kimura/
- kimura@dce.osaka-sandai.ac.jp
軽くしなやかに踏み切ってこそ、遠くに飛べる
 礼儀こそが「美」である。目立たず、地味に、黙々と苦労を厭わない、というのが理想ではないか。 バタバタせずに、軽くしなやかに踏み切ってこそ、遠くに飛べるというものである。
礼儀こそが「美」である。目立たず、地味に、黙々と苦労を厭わない、というのが理想ではないか。 バタバタせずに、軽くしなやかに踏み切ってこそ、遠くに飛べるというものである。
担当授業
- 基本科目
-
- 中国語
- 展開科目
-
- 中国文化論
- 実践科目
-
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 中国文化
- 中国文学
- 研究テーマ
-
- 北京作家老舎
-
中国現代文学の作家では、「異端」と称してもよい北京出身の老舎。 老舎の「ことばの芸術」を解読するとともに、文学言語としての北京語を考察。
- 租界上海
-
ここで言う「租界上海」とは、ズバリ「租界=上海」のこと。 従来、「悪の象徴」たる「上海の租界」としかとらえられることのなかった「租界」の復権を願い、租界文化の本質に迫りたい。
- 北京の胡同(Pekinology)
-
北京の文化環境を考える上で重要な位置を占める胡同の「ほろ美」を通して、北京の文化を考究。 「北京の胡同(路地)」をもじって、「Pekinology」と称す所以である。
連絡先
- 研究室
- 14907
- kurahashi@dce.osaka-sandai.ac.jp
ときには立ち止まって思考しよう
 大学ではとくに、物事について多角的な視点から考えるという方法を身につけてほしいと思います。自分が見て、わかっていると思い込んでいる世界がすべてなのか、別の見方はありうるのか、そこからもう少し外へと開かれることはないのか、自分に問いかけてみてください。思考することは、大学にいる間だけでなく、社会に出てからも、さらに言えば生き続ける限り、みなさんの力となります。思考することをよく生きるための助けとしてください。
大学ではとくに、物事について多角的な視点から考えるという方法を身につけてほしいと思います。自分が見て、わかっていると思い込んでいる世界がすべてなのか、別の見方はありうるのか、そこからもう少し外へと開かれることはないのか、自分に問いかけてみてください。思考することは、大学にいる間だけでなく、社会に出てからも、さらに言えば生き続ける限り、みなさんの力となります。思考することをよく生きるための助けとしてください。
担当授業
- 基本科目
-
- 人間環境学概論
- 展開科目
-
- 大衆文化論
- メディア文化論
- 実践科目
-
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- フランス哲学
- 社会情報学
- 研究テーマ
-
- 二元論の問題
-
デカルトにおける想像の問題を、心身の区別と合一の両立と関連づけて考察すること。
- 情報倫理の問題
-
効率性や有益性といった視点から語られることの多いサイバースペースを、知の空間 --- 集合的知性として捉え直して積極的な倫理を語ること。
連絡先
- 研究室
- 14415
- soga@dce.osaka-sandai.ac.jp
フレンドリーな雰囲気が文化コミュニケーション学科の魅力
 わたしたちの学部・学科の魅力は4年間一貫教育と少人数制の授業にもとづくフレンドリーな雰囲気だと思います。 その中で各自が自分の意見を持ち発表できるようになることを学びますが、学生さんたちが次第に自信をつけて立派になってゆく過程を見守るのは、
わたしたちにとって大きな喜びです。キャンパスの学生さんたちは美しいスマイルと会釈を忘れませんし、遠くからも見つけて声をかけてくれます。 英語の授業も担当しているので、英語で挨拶をしてくれる人も多いんですよ。英語は嫌いという人も大丈夫です。
わたしたちの学部・学科の魅力は4年間一貫教育と少人数制の授業にもとづくフレンドリーな雰囲気だと思います。 その中で各自が自分の意見を持ち発表できるようになることを学びますが、学生さんたちが次第に自信をつけて立派になってゆく過程を見守るのは、
わたしたちにとって大きな喜びです。キャンパスの学生さんたちは美しいスマイルと会釈を忘れませんし、遠くからも見つけて声をかけてくれます。 英語の授業も担当しているので、英語で挨拶をしてくれる人も多いんですよ。英語は嫌いという人も大丈夫です。
担当授業
- 基本科目
-
- コミュニケーション英語
- 展開科目
-
- 英米文化論
- 実践科目
-
- コミュニケーション演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 中世英文学
- 研究テーマ
-
- 中世西洋写本研究
-
おもに15世紀に書かれた手書きの本(写本)の研究および校訂。
- 14・15世紀の宗教文学と一般信徒の信仰:写本文献の伝播と変容に基づく研究
-
特に、キリストと聖母の生涯と受難の黙想を題材とした宗教文学の研究、本文校訂、翻訳。
連絡先
- 研究室
- 14208
- taguchi@dce.osaka-sandai.ac.jp
物事をじっくり考える
 私自身の大学時代を振り返ってみますと、「物事をじっくり考える」という時間を多く持った記憶があります。本を読み、文を綴り、人と話し、また自分で考える。社会に出る前に、物事をじっくり考えること、これを大事にしてください。
私自身の大学時代を振り返ってみますと、「物事をじっくり考える」という時間を多く持った記憶があります。本を読み、文を綴り、人と話し、また自分で考える。社会に出る前に、物事をじっくり考えること、これを大事にしてください。
担当授業
- 基本科目
-
- 上級日本語
- 展開科目
-
- 文章表現論
- 日本文化論
- 実践科目
-
- プロゼミナール
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 日本語教育学
- 日本語学
- 研究テーマ
-
- 教師間協働の研究
-
海外の日本語教育の現場には、現地の日本語教師と日本人の日本語教師との間における協働が増えてきています。この教師間協働にはどのような課題があるのか、その課題をどのように乗り越えることができるのかなどを質的な調査方法を駆使して調査・分析しています。
- 留学生の留学体験の研究
-
日本語を学ぶ留学生は、様々な背景や学習目的を持ち日本にやってきます。その留学生活や学習経験の中で、どのような困難を感じ、どのような成功体験を持っているのでしょうか。それを解明し、これから留学する外国人の方々へ還元できれば、実りの大きい留学が体験できるはずです。
- 映画の教材価値論の研究
-
映画は、娯楽のためにあるだけではありません。日本語を学ぶ際の教材としての価値も持つものです。日本の映画にはどのような教材価値があるのか、それをどのように加工すれば教材価値が生み出されるのかを考察します。
- 現代日本語のリアリティの研究
-
現代日本語の事実性や仮定性といったリアリティの意味は、どのような構造で表され、どのような機能を持つのかを研究しています。
- 予測文法の研究
-
日本語母語話者や外国人日本語学習者は、日本語を聞いているときに、次に続く日本語をどのように予測しているのでしょうか。古くて新しい予測文法の解明にはまだわからないことがあります。
- 談話(雑談)の研究
-
日本語母語話者はカジュアルなおしゃべり(雑談)をどのように行っているのでしょうか、またその雑談を日本語学習者は、どのように聞きとっているのでしょうか。おしゃべり(雑談)の構造や学習者の聞きとりの困難点を調査しています。
連絡先
- 研究室
- 14508
- nakayama@dce.osaka-sandai.ac.jp
「人としての器」を大きくしよう
 大学は自分の人間性を大きくする所ですので、勉強だけでなくサークルやクラブ活動を頑張ってみたり留学してみたり友人と遊んだりバイトをしたり、 できるだけ色々な経験をして「人としての器」を大きくして欲しいなと思います。
ただ、その一方では、社会人になる前の大切な時期でもありますので、「ホウ・レン・ソウ(報告、連絡、相談)」や 社会人としてのマナーもしっかり学んで卒業していって頂きたいです。
素敵な想い出がたくさん残る有意義な大学生活を送って下さいね!
大学は自分の人間性を大きくする所ですので、勉強だけでなくサークルやクラブ活動を頑張ってみたり留学してみたり友人と遊んだりバイトをしたり、 できるだけ色々な経験をして「人としての器」を大きくして欲しいなと思います。
ただ、その一方では、社会人になる前の大切な時期でもありますので、「ホウ・レン・ソウ(報告、連絡、相談)」や 社会人としてのマナーもしっかり学んで卒業していって頂きたいです。
素敵な想い出がたくさん残る有意義な大学生活を送って下さいね!
担当授業
- 基本科目
-
- 心理学の基礎
- 展開科目
-
- 発達心理学
- 心理学研究法
- 実践科目
-
- コミュニケーション演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 臨床心理学
- 健康心理学
- メンタルヘルス
- 研究テーマ
-
- 不登校
-
不登校の助長及び抑制要因に関する研究すると共に、抑制要因を利用した学内での不登校支援体制を研究している。
- メンタルヘルス
-
学校におけるメンタルヘルス教育のあり方、ならびに一般の人々の心身の健康の維持・増進について研究している。
連絡先
- 研究室
- 14409
社会のありかたは歴史の積み重ね
 今、私たちが生きているこの社会のありかたは、歴史的な積み重ねのうえに形作られています。例えば、毎朝決まった時間に起きて、朝食をとり、学校や会社へ遅刻しないように行く。こうしたごく日常的な行動も、少し時代をさかのぼると決して当たり前のものではなく、社会の変化にともなって現れた比較的新しい習慣といえます。この大学での4年間の勉強を通じて、毎日の生活のいろいろな側面について歴史的に考えてみてください。
今、私たちが生きているこの社会のありかたは、歴史的な積み重ねのうえに形作られています。例えば、毎朝決まった時間に起きて、朝食をとり、学校や会社へ遅刻しないように行く。こうしたごく日常的な行動も、少し時代をさかのぼると決して当たり前のものではなく、社会の変化にともなって現れた比較的新しい習慣といえます。この大学での4年間の勉強を通じて、毎日の生活のいろいろな側面について歴史的に考えてみてください。
担当授業
- 基本科目
-
- 日本と西洋
- 展開科目
-
- ヨーロッパ文化論
- 実践科目
-
- プロゼミナール
- ゼミナール
- 卒業研究
- 教職科目
-
- 外国史概論
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- イギリス帝国史
- 上海史
- 研究テーマ
-
- 上海租界における外国人居留民社会
-
上海に租界という形で西洋的な社会を築き上げたイギリス人。彼らはどのような都市制度を上海に実現し、運営したのか、また現地の圧倒的多数の中国人や、大陸進出を目指し大挙して上海にもやってきた日本人とどのような関係を結んだのかを考察する。
- 戦時下上海における劇場文化
-
租界成立期にイギリス人素人劇団の専用劇場として始まったライシャム劇場は、上海における舞台芸術の中心的存在であった。太平洋戦争中に日本軍に接収された後も、日本の文化工作の場となり、演劇、交響楽コンサート、バレエ、オペラ、中国話劇、演芸など様々な舞台芸術が上演され、かつてない多様性をみせることになる。このライシャム劇場に注目することで、戦時下の上海における文化状況を明らかにしたい。
連絡先
- 研究室
- 14404
- fujita@dce.osaka-sandai.ac.jp
挑戦こそが未来を切り拓く
 大学生は人生で最も自由な時期です。時間に比較的余裕があり、周囲からも大人扱いされ、生活のために誰かの顔色をうかがうこともほとんどないはずです。でも、せっかく与えられたこの「自由」を浪費してしまうと、その後の人生につけが回ってくることになります。私が勧める「自由」の活かし方は、ただ一つ。何事にもチャレンジ精神を失わないということです。挑戦することで得られた体験こそが、みなさんの将来を切り拓いてくれることでしょう。私たちは挑戦するみなさんをしっかりサポートしていきます。
大学生は人生で最も自由な時期です。時間に比較的余裕があり、周囲からも大人扱いされ、生活のために誰かの顔色をうかがうこともほとんどないはずです。でも、せっかく与えられたこの「自由」を浪費してしまうと、その後の人生につけが回ってくることになります。私が勧める「自由」の活かし方は、ただ一つ。何事にもチャレンジ精神を失わないということです。挑戦することで得られた体験こそが、みなさんの将来を切り拓いてくれることでしょう。私たちは挑戦するみなさんをしっかりサポートしていきます。
担当授業
- 基本科目
-
- 日本と韓国・朝鮮
- 朝鮮語海外研修
- 展開科目
-
- 韓国・朝鮮文化論
- アジア近代史
- 実践科目
-
- フィールド演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 朝鮮近現代史
- 東アジア交流史
- 研究テーマ
-
- 植民地公娼制度・日本軍「慰安婦」制度について
-
戦前の日本帝国の支配地域における公娼制度と、朝鮮人接客女性の生活実態を分析することで、 「帝国」日本の性支配システムを明らかにし、またこれが日本軍「慰安婦」制度に継承される過程を考察する。
- 植民地期・解放直後の済州島の社会運動について
-
日本統治下の植民地朝鮮において、とくに大阪と関係の深かった済州島の民族解放運動の展開過程を、 解放後の4・3事件(1948年)や在阪朝鮮人の生活状況などとの関係性を念頭におきつつ検討する。
- 韓国の「過去清算」について
-
現在、韓国で進められている「過去清算」の事業の歴史的意義を、朝鮮現代史の流れをふまえながら、世界史的な観点から検討する。
連絡先
- 研究室
- 14407
- ホームページ
- http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~funtak/
- funtak@dce.osaka-sandai.ac.jp
日常生活に活かす知識
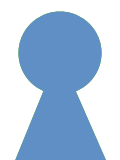 文化コミュニケーション学科では,文学や語学,社会学,歴史学,哲学,心理学など,多様な視点から様々な知識を深めることができます。それらの知識を日常生活のあらゆる状況と関連づけて個々の中で再定義させ,得た以上のものに高め,活かしていってほしいと思います。
文化コミュニケーション学科では,文学や語学,社会学,歴史学,哲学,心理学など,多様な視点から様々な知識を深めることができます。それらの知識を日常生活のあらゆる状況と関連づけて個々の中で再定義させ,得た以上のものに高め,活かしていってほしいと思います。
担当授業
- 基本科目
-
- 心理学概論
- 展開科目
-
- 学習心理学
- 健康心理学
- 実践科目
-
- コミュニケーション演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- 認知心理学
- 発達心理学
- 教育心理学
- 研究テーマ
-
- 嗅覚と記憶
-
嗅覚と記憶における独自な関係性や,嗅覚刺激により記憶が想起される認知メカニズムについて研究を行っている。
- アイデンティティと記憶
-
アイデンティティと記憶の関係性およびアイデンティティを支える記憶の機能について研究を行っている。
- 情動知能
-
情動を扱う個人の能力である情動知能の測定および記憶成績への影響について研究を行っている。
- TOT(Tip of the Tongue)現象
-
TOT(喉まで出かかっているにもかかわらず,その対象を思い出せない)現象の生起メカニズムの解明や解決への手立てについて研究を行っている。
連絡先
- 研究室
- 14510
- kyamamoto@dce.osaka-sandai.ac.jp
問題は乗り越えるために存在する
 問題のない人生は有り得ない。そして自分で問題解決方法を見つけられらないとき、家族、友達や知人に相談する。 自分が考えられる解決方法よりも他のいくつかの手段があることを忘れずに! 問題は乗り越えるために存在する。
問題のない人生は有り得ない。そして自分で問題解決方法を見つけられらないとき、家族、友達や知人に相談する。 自分が考えられる解決方法よりも他のいくつかの手段があることを忘れずに! 問題は乗り越えるために存在する。
担当授業
- 基本科目
-
- 比較社会論
- 比較文化論
- 展開科目
-
- 民族とマイノリティ
- コミュニケーション演習
- 実践科目
-
- フィールド演習
- ゼミナール
- 卒業研究
専攻分野/研究テーマ
- 専攻分野
-
- ethnic minorities
- 移民労働者
- 難民
- 研究テーマ
-
- ブータン難民
-
ネパール東部のキャンプに住んでいるブータン難民の歴史と現状(特に教育問題)を分析している。
- ドイツとオーストリーの移民労働者と難民
-
ドイツとオーストリーにおける移民労働者と難民の生活条件(法的地位、宗教、教育)
- 在日韓国・朝鮮人の歴史
-
1945年までの歴史、特に同化政策の実施について
連絡先
- 研究室
- 14410
- ringoman@dce.osaka-sandai.ac.jp